 成長
成長 文化とゆとり
土地の文化であれば、その土地の住民が育むものだ。住民が時間やお金を使うことで育まれる。ぎりぎりの生活の中でも文化を育むことはできるが、ゆとりや余裕があると文化に奥行きが出る。日本各地にある多様で豊かな文化は、どんな風にゆとりや余裕が生まれ、...
 成長
成長  きづき
きづき  きづき
きづき  ありのまま
ありのまま  広がり
広がり  きづき
きづき  広がり
広がり  刺激
刺激  仲間
仲間  俯瞰
俯瞰  仲間
仲間 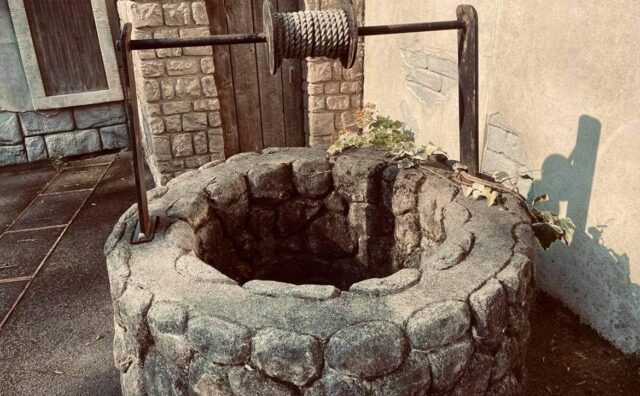 文化
文化  きづき
きづき  ゆとり
ゆとり  ゆとり
ゆとり  成長
成長  俯瞰
俯瞰  仲間
仲間  妄想
妄想  きづき
きづき